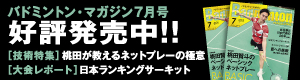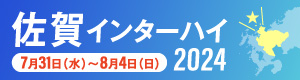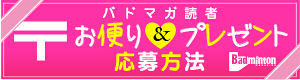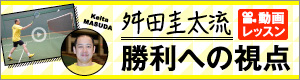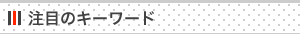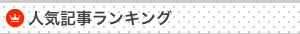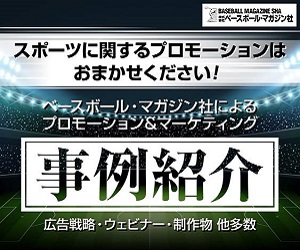国内実業団のトップカテゴリーであるS/Jリーグに属する丸杉女子バドミントン部が、独立運営を行なうプロチーム『岐阜Bluvic(ブルヴィック)』として、活動をスタートさせたのは、2024年4月。岐阜Bluvicには、丸杉の選手として活躍してきた福島由紀や廣田彩花が所属。24年11月に開幕したS/Jリーグ2024では、ブロック上位2チームが進出できるTOP4への進出を決めている(S/Jリーグ2024 TOP4は25年2月21日、22日に横浜BUNTAIで開催)。
同クラブはファンクラブを立ち上げ、自前の丸杉アリーナでは、バドミントンスクールを開校している。プロクラブ化の経緯やメリット、めざす先などを同クラブの杉山幸輔社長にインタビューし、その取り組みをレポートする。

S/Jリーグに所属する岐阜Bluvicは、丸杉バドミントン部からプロクラブに形を変えたチームだ。運営会社を新たに立ち上げて独自経営に踏み切ったのは、今年4月。以降、選手は拠点である丸杉アリーナでのスクール活動や、岐阜県内のイベント参加など、地域での交流活動を盛んに行なっている。プロクラブ化の理由は何か。今後どのように変わるのか。
新たな運営会社である、株式会社岐阜Bluvicの杉山幸輔社長に話を聞いた。
「一番大きな理由は、バドミントンを国内でもっと盛り上げるためには、企業スポーツではなく、クラブチームの方が適していると考えたからです。プロ野球もサッカーもバスケットも、今はプロクラブ化して(会社だけに頼らず)自分たちでお客さんをつくってマネタイズをして、事業を成立させるようになっています。バドミントンだけ、この波が来ないわけがありません。いち早く土台をつくりたいと思い、分社化することで意思決定をスムーズにしようと考えました」(杉山社長)
活動資金の生み出し方を変えることが、競技の活性化と連動する。少し説明が必要だろう。実業団にも、プロクラブにも、メリットとデメリットがある。日本が経済発展を続けた時代に実業団スポーツの文化は強まった。選手は社員として雇用され、生活が安定する。チーム活動の費用も、会社が組んだ予算を使うのみ。しかし、あくまでも社員。会社が求める以上の活動をすることは、難しい。チームとしてファンの獲得が必要だと感じても、会社は余計な活動を求めず、現場も社業と認められない仕事は避ける。例えば、S/Jリーグの観客動員の少なさが話題に上がることがある。競技人気を高めるためには改善が必要だと考える人は多いが、チケット収入でリーグやチームの運営を賄っているわけではなく、当事者は誰も困っていないため、実際に動くのは意外と難しい。社内を活性化するために存在するチームは、会社の意向がなければ身動きが取れない。岐阜がプロ化できたのは、丸杉の創業一家で取締役でもある杉山社長が主で動いたからで、稀なケースだ。
また、今の日本は、不景気が続いている。バドミントン界でも、チーム消滅の悲しい歴史があるが、実業団は、1社の決定だけでチームが消滅しかねない。一方、プロクラブは、予算をもらって使うだけの資金繰りではなく、地域やファンに楽しみを与え、チケットやグッズ販売、スポンサードなどで資金繰りを行なう循環型をめざす。競技成績だけをめざせばいい状況から、多方面でクラブの価値を上げる必要性があるが、ファン獲得が生命線のため、競技活性化に直結する。また、地域の複数のスポンサーに支えられれば、チーム消滅のリスクを分散できる。
プロ化は、よほど人気がなければうまくいかないと考える人は多い。多くの人がマスメディアを通じてスポーツにふれてきたからだ。しかし、現在の日本のプロスポーツの多くは、全国にファンをつくるのでなく、地元にファンをつくることを重視している。地元で企業や行政、人を媒介する存在となり、地域で価値を持てれば、地元を中心に複数の企業からサポートを得ることが可能になる。国や企業などのサポート団体から予算が降ってくる形に限界が訪れようとしている時代。1社が支える実業団形式でなく、プロ化によって自営するスタイルでなければ、継続的な活動は難しい――そんな考え方が、日本のスポーツ界に広まっている。
クラブがめざす今後
運営体制の今後について、杉山社長は次のように話した。
「ロス五輪(2028 年)くらいのタイミングでは、丸杉がメインで、半分くらいは他の企業の皆さんに支えられるようなチームになってほしい。多くの企業に支えられるチームでありたいし、リスク管理の面でも、万が一、丸杉が苦しくなっても(ほかにもサポート企業がいてチーム運営費の)コストカットを少しやれば頑張れる状態にしておかないといけないし、その方がサステナブル(持続可能)。岐阜にバドミントンチームがあって、五輪出場選手になった福島由紀/廣田彩花を筆頭に、日本のトップレベルの選手が来てくれた。来年には、世界ジュニア女王になった岐阜県出身の平本梨々菜選手も入ってくれる。そんな状況になったのに、大人の事情でチームが消えてしまったらよくない。スポーツチームをどう育んで、岐阜の活性化に還元するか。岐阜県、岐阜市とも話していて、一緒に絵を描かないといけません」
S/Jリーグの状況をイメージしてほしい。試合会場のスタンドで目立つのは、チーム=会社の応援団だ。競技ファンもいるが、少数。選手も「会社のために」と話す。狭い世界に向けられた競技大会になっている。一方、プロ野球やプロサッカーのJリーグ、プロ化したバスケットボールのBリーグ、今秋から新リーグとなったバレーボールのSVリーグは、ホームチームを応援する地元のファンが主役だ。チームは、より多くの人に支えてもらうため、実業団スタイルからプロクラブへ運営を変更。チーム名から企業名を外して地域名を押し出すなど地域密着化を進め、活動拠点を中心に周辺企業との協業体制を推し進めている。
岐阜Bluvicも同様に、チーム名を変更。プロクラブ化後、選手が指導するバドミントンスクールを開始したほか、町のイベントへの参加、商業施設での競技アピールイベント、老人ホームの訪問など、さまざまな活動を行なっている。杉山社長は「プロクラブ化したことで、選手の意識は明らかに変わりました。その活動をやらねばならない意味が変わる。これまでは、会社のため。でも、今は、誰のためにやるのかと聞かれたら、ファン(になってくれる地域の人)のためと答える。だから、スクールやイベントでの発言もどんどん本気の言葉になっている」と最初の変化を感じている。
インサイド・レポート2に続く

杉山幸輔(すぎやま・こうすけ)
慶応義塾高、慶応義塾大を卒業し、電通で新聞広告法人営業やDXコンサルなどを担当。在籍中にグロービズ経営大学院にてMBAを取得。2022年に電通を退社し、同年、家業の株式会社丸杉に入社。丸杉では取締役として人事、デジタル、広報を担当。2024年4月、岐阜Bluvicの社長に就任。中学、高校、大学ではラグビーをプレー。

取材・文/平野貴也 写真/平野貴也、岐阜Bluvic提供
(※この記事はバドミントン・マガジン2024年12月号に掲載された内容です)